同じ障害でも悩みが正反対。ADHDの私の在宅勤務の工夫4選。
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.1.25

ADHD当事者で2年在宅勤務をしてきて、困ったのは「集中できない」ということ。今回は、在宅勤務のための工夫を4つご紹介しながら、他のADHD当事者ライターの記事と比較して、共通点やちがいについて考えてみます。
執筆:森本 しおり Morimoto Shiori
以前、同じくパラちゃんねるカフェのライターのとくらさんの『ADHDの私が在宅勤務で失敗したこと4選』という記事がありました。
私はとくらさんの原稿を読んで「同じADHDなのに悩みが正反対だ!」と驚きました。詳しくは、ご本人の原稿を読んでいただきたいのですが、とくらさんの悩みの多くは過集中から来るもの。そして、集中しすぎないための工夫がされているのです。
私もADHDの当事者で2年以上テレワークをしていますが、悩みの中心は「集中できない」ということ。そう、過集中は滅多に訪れません。今回は、私の在宅勤務の工夫を4つご紹介しながら、同じ障害を持つ人の共通点やちがいについて改めて考えていきたいです。

①薬を飲む
一つ目にして最強。薬を飲むことです。ADHDの診断を受けている人しかできない方法ではありますが、効果は一番わかりやすいです。
かなり少ない量ではありますが、ADHDの薬を2種類飲んでいます。ストラテラ25mgと、コンサータ18mgを一錠ずつ。私自身の場合、特にコンサータは集中に直結すると感じています。
薬を飲むとソワソワと気が散ることが少なくなり、集中力がプツリと切れる瞬間も減ります。飲み忘れるとボーっとしたり、昼間でも眠気がやって来たりします。
ここだけの話、昔はどれだけ「今は集中しなきゃ!」と思っていても、会議中や研修中に居眠りしてしまうこともありました。薬を飲み始めてからは居眠りがピタッと無くなったことに感動。レベルの低い話で申し訳ないですが、居眠りはけっこう切実な悩みでした。
②環境を整える
二つ目は、環境を整えることです。
2年くらい前まではライターの仕事の日はコワーキングスペースに出勤していたのですが、コロナ禍のためにテレワークになりました。そのタイミングで、自宅にデスクとオフィスチェアを買いました。集中するための部屋を作らないと、どうも仕事がはかどらなかったのです。
とくらさんは「集中し過ぎないためにテレビのワイドショーを流している」と書かれていましたが、私は真反対です。
私は、気の散る要素を徹底的に排除しています。真っ白な壁に向かって、無音で仕事しています。デスクにも、余計なものは一切置きません。視界にも聴覚にも、注意を引くものは無くしたい。仕事以外何も目に入らないくらいが望ましいです。
③仕事前のルーティーンを作る
三つ目は仕事前のルーティーンを作ることです。そろそろ伝わってきているかもしれませんが、私はとにかく「気分の切り替え」が苦手なのです。
出勤しているときは、通勤の時間帯に少しずつ仕事モードになっていきました。場所の力も大きいです。職場は「仕事をする場所」と認識しているので、自然とシャキっとできます。
しかし、コロナ禍によって出勤がなくなったことで通勤時間の節約にはなったものの、仕事の効率が下がりました。仕事のやる気が全然出なくなってしまったのです。
そこで、気分の切り替えのために「仕事前に15分くらい外を散歩する」をマイルールにしました。一回、外に出て体を動かしながら、少しずつ仕事モードにしていきます。散歩に行き、ご飯を食べて、飲み物を用意して、机を拭く。10分前くらいになったら、一日の仕事を確認することをルーティーンにしました。
④こまめに休憩をとる
最後は、こまめに休憩をとることです。
私も、他のADHDの方達と同じように過集中になることはあります。周りが全く気にならず、目の前のことに没頭して時間を忘れてのめりこむゾーン状態。ただ、私の過集中はそこまで長続きしません。
私が休憩をこまめにとるのは、休憩を挟まないと集中力が続かないからです。しょっちゅう立ち上がったり、トイレに行ったり、お茶やコーヒーを飲んだりしています。落ち着かない人ですみません。
1時間に1回くらい立ち上がってストレッチしそして、3時間に一回くらい長めの休憩をとります。休憩をとった方が、全体的な仕事の効率は上がると感じています。

同じ障害を持っている二人の共通点と相違点
今回は、ADHDの私が在宅勤務をするときの工夫について、同じくADHD当事者のとくらさんの原稿と比較しながらまとめました。
とくらさんの原稿を読んで「そういえば、私はミーティングの時間を忘れたことはないなあ」・「トイレや水分補給は多すぎるくらいだなあ」と気づきました。ソワソワ立ち上がってしまうことは欠点だと思っていたのですが、少なすぎて困っている人もいるのだなぁと目からウロコが落ちました。
ただ、過集中も集中できないことも「ほどよく集中する」が上手くできないところは共通しています。
だからこそ、対策として「休憩を決めておく」や「環境作り」という、外側の枠組みで調整しているのかもしれません。「気を付けよう」という意識だけだと同じ失敗をしがちなので、時間や空間の区切りなど、仕組みを変えてしまう方が楽で長続きします。
障害が同じでも、悩みや対策は変わるものなんだなぁと改めて感じました。他の皆さんはどうなんでしょうか?



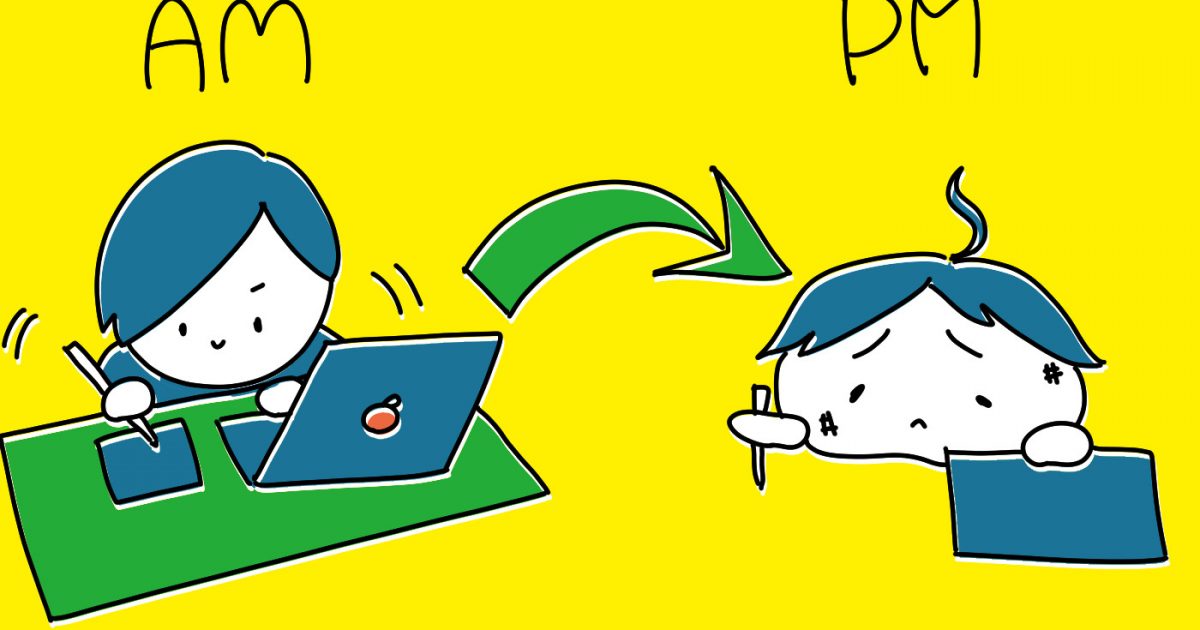

















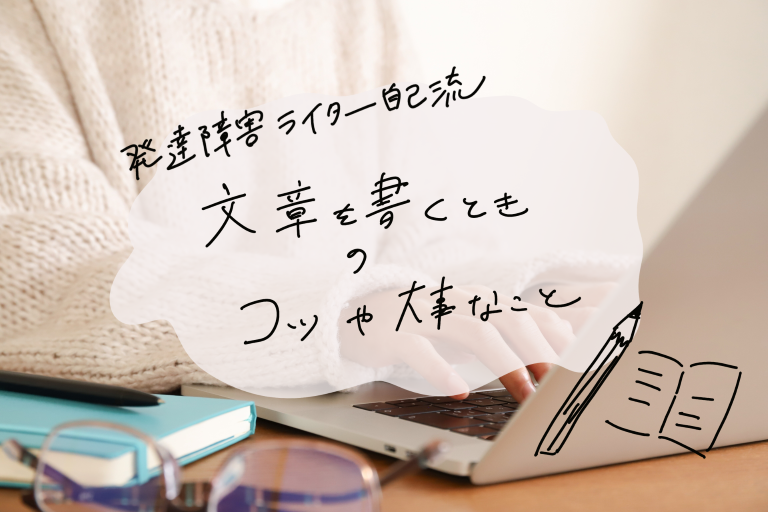

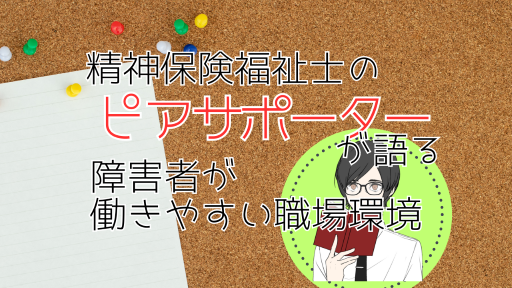
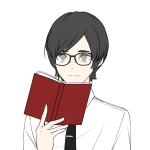
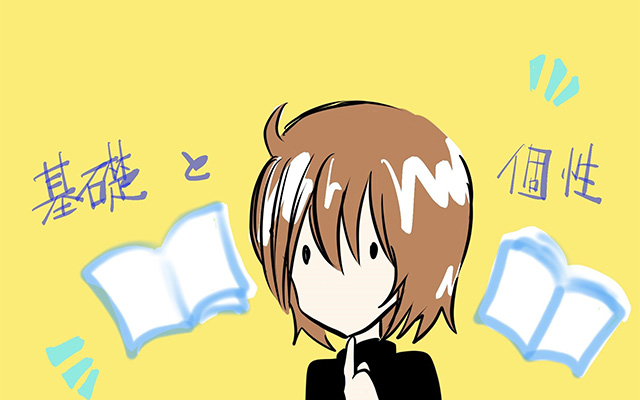








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック