障がい者雇用で働くことが社会貢献に繋がっている。株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 企画本部経営管理部 岩井崇志さんインタビュー
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.2.18

『パラちゃんねるカフェ』がお届けする障がい者雇用に取り組む企業インタビュー。写真は左からマネジャー 中村忠さん、岩井崇志さん、総括マネジャー 南大輔さん。今回は、株式会社セブン‐ イレブン・ジャパン(以下、セブン‐イレブン・ジャパン)で働く企画本部経営管理部 岩井崇志さんにお話を伺いました。
執筆:株式会社セブン&アイ・ホールディングス
はじめに
セブン‐イレブンやイトーヨーカドーなどの店舗でお馴染みのセブン&アイグループ。セブン‐イレブン・ジャパンは、コンビニエンスストア「セブン‐イレブン」のフランチャイズチェーン本部として、全国21,227店舗(2021年12月末時点)ある加盟店の経営のバックアップを担っています。
今回、お話を伺った岩井崇志さんは、セブン‐イレブン・ジャパンの企画本部経営管理部で働いています。
岩井さんは生まれつき聴覚に障がいがある感音性難聴です。聴力は、補聴器を装着していても目の前でなる飛行機のエンジン音が聞き取れる程度で、補聴器でも聞き取れないことが多いそうです。普段は、口話、筆談、音声認識ソフトを活用してコミュニケーションを取っています。
普段のお仕事の内容ややりがい、働く上での工夫など、さまざまなお話を伺いました。
 セブン‐イレブン・ジャパン本社
セブン‐イレブン・ジャパン本社
障がい者雇用で働くことで社会に貢献出来ていると実感している。
岩井さんはセブン‐イレブン・ジャパンに入社して16年目。これまで勤労厚生、給与関連、ダイバーシティ推進など人事のスペシャリストとしての経験を重ね、現在は企画本部経営管理部に所属し、健全な企業経営を目指したガバナンス強化を推し進める一員として情報セキュリティを担当しています。
主に設備やルールなどのハード面と部署への教育などのソフト面の管理を担当しています。社員に対する教育計画、e-learning、情報管理体制の確認など各組織本部とコミュニケーションをとりながら、情報漏洩リスクを防ぐためのガバナンスを意識して進めています。
情報セキュリティは難しいイメージが先行するため、いかに簡単にわかりやすく伝えるかを追求しており、「わかりやすかった」「ありがとう」と言われると明日もまた頑張ろうと思えます。
セブン‐イレブン・ジャパンでは聴覚障がい者への配慮として口話、筆談、音声認識ソフトを適用しており、岩井さんは聴覚障がい者の視点から社内のノーマライゼーションを推進する役割も担っています。
入社16年を経て聴覚障がいのある後輩は17名になりました。私が率先して障がい特性やお願いしたい配慮を発信することで後輩も働きやすい環境が作りやすくなると思っています。
障がい特性を説明した自己紹介資料を作成したり、メールの署名に障がいがあることを記したりと初対面でも相手の不安が軽減される工夫を積極的に発信しています。
岩井さんは障がい者雇用として働く責任を全うすることが社内だけでなく社会貢献にも繋がっていると話します。セブン‐イレブンには、1日に全国で約2,100万人、1店舗あたり約1,000人が訪れます。社員や加盟店の障がいに対する理解が深まることでコンビニエンスストアから地域のノーマライゼーションを推進することを目指しています。
 企画本部経営管理部 岩井崇志さんの仕事風景
企画本部経営管理部 岩井崇志さんの仕事風景
働くためのセルフアドボカシーの大切さ
家族の中で唯一、聴覚に障がいがある岩井さんは高校まで普通学級へ通い、授業は何もわからなかったと話します。大学で初めて聴覚障がいを自覚し、聴覚障がいとは何かを学び、そして、コミュニケーションの手法として口話以外に、筆談や手話、メールの活用などを学ばれました。
自身の経験も踏まえ、社会人になるまでにセルフアドボカシーを獲得することが大切さだと考えます。コロナ禍による在宅勤務でオンライン会議が浸透したことは聴覚障がい者にとって筆談や個別サポートを利用しづらい環境を生みました。特性や困りごとを適切に説明できることでZoomの字幕機能や音声認識ソフトAmiVoiceの活用など課題を早く解決することが可能になります。
※セルフアドボカシーとは、「自己権利擁護」のことで必要なサポートを相手に説明して理解してもらう活動です。
学校生活の中で失敗の体験が続き、自己肯定感が低く、漠然とした不安を抱えている障がいのある方も少なくありません。岩井さんが障がい者雇用で働くうえで大切にしていることを教えてください。
働くうえで大切にしていることは二つあります。
一つ目は、「セルフアドボカシー」です。障がい者として何ができるのか、できないのか、自分を知らなければ相手に伝えることができません。まずは自分の障がい特性を知り、相手に説明できるように努めることです。
二つ目は、「可能性への挑戦」です。
目の前の仕事を素直に取り組むことで、周囲から信頼を得ることができます。一歩ずつ仕事の挑戦をすることで、自らの成長に繋がり、また信頼の積み重ねが自己肯定感を高めることにもなります。「セルフアドボカシー」と「可能性への挑戦」の二つこそが働きやすい環境になっていくのではないでしょうか。
 左から中村忠さん、岩井崇志さん、南大輔さん
左から中村忠さん、岩井崇志さん、南大輔さん
さいごに
今回の取材では、総括マネジャー 南さん、マネジャー 中村さんにも同席いただきました。最後に障がい者雇用を進めることで実感した変化・効果があれば教えていただけますでしょうか。
一番の変化は、言葉の伝え方、物事の発信の仕方を見直すようになった点です。事前にメールを送る、理解度を確認するなど社内に配慮が生まれ、コミュニケーションのズレや齟齬が低減されたと感じています。
ありがとうございました。岩井さんは、「周りの当たり前は当たり前でない」と話し、環境に対する感謝と真摯に業務に取り組む姿勢がとても印象に残るインタビューとなりました。
取材後記
先天的な障がい特性や環境から障がいを自覚せずに高校・大学へと進学する方も少なくなく、セルフアドボカシーの獲得は簡単なことではありません。
働く準備として親や学校の先生、就労支援機関などのサポートを受けながら、障がい特性を把握し、相手に説明する練習をしてみるのも良いかもしれません。
社会インフラとなるコンビニエンスストア「セブン‐イレブン」から地域にノーマライゼーションが広がっていくことに期待したいと思います。
Text by
株式会社セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイグループは、コンビニエンスストア、食品スーパー、GMS、百貨店、専門店など、多様な業態を通じて、お客様の生活ニーズに幅広く応え、障がい者雇用を積極的に進めており、グループ企業で採用実績がある他、北海道北見市には特例子会社のテルべもある。
採用情報はこちらをクリック
















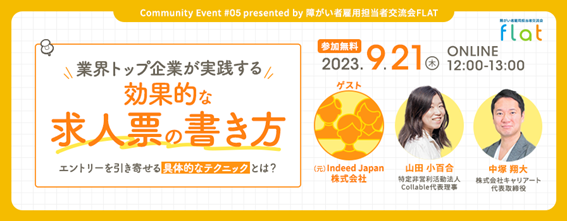








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック