自分に「厳しい」ことがかえって成長を阻んでしまう。
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.3.28

人は機械ではありません。
わけもなくいつもよりうまくいかないと感じることも、やる気が続かないこともあります。
でも、その「変化」のたびに自分自身を傷つけている方は意外と多いようです。
執筆:いりえ(北橋 玲実)
発達障害は、とても疲れやすい特性を持ちます。「易疲労性」とも呼ばれますが、人と同じ作業をしていても、余計なことに気を取られて思考や意識にエネルギーを過剰に使い続けて消耗してしまうのです。
健常者と同じように思考しようとしても、関連する情報を適切に引き出して活用することが難しく、脇道に逸れ、その脇道からさらに脇道へ…というループを繰り返し、「あれ、何してたっけ?」となってしまうこともしばしば。
もちろん、いろんな方向に思考を広げることにより、普通の人が生み出せない新しいアイデアや深い思考にいたることもあるかもしれません。
しかし、日常生活において、ごみを出す程度の簡単な作業を行うために、例えば台所の生ごみを回収するだけのつもりが、シンクの汚れ、鍋の洗い物、浄水器のフィルターの期限切れなどなどが気になってしまい、結局ゴミ出しの時間を過ぎてしまう、なんてこともあります(体験談かもしれません)。
ゴミ出しくらいなら日を待てば問題なく済ますこともできますが、ささいなことで思考力も体力も消耗してしまうのが発達障害者です。
もちろん健常者であったとしても、ストレスフルな社会や家庭の不和、経済的な不安を助長するメディアの存在、友人関係における劣等感の醸成など、心身を消耗させる要因は避けられず、私たちは常に消耗していることは間違いありません。
しかし、心身の健康状態がどうであろうと、情報や組織の指示にまみれ「やるべきこと」をただひたすら追いかける生活に当たり前のようになじんでしまっている人も少なくないでしょう。

常に高いパフォーマンスを要求され、時間の制約も厳しく設定され、プレッシャーに強くさらされる毎日。その日々の中で思うように調子が出ず、やるはずのことができない瞬間は、計り知れないストレスがかかるものです。
しかし、人は機械ではありません。調子がいい日もあれば悪い日もあるのです。
人の肉体も精神も、気圧や気温に始まり、他人の声や存在を感じて過剰にやきもきしてメンタルをすり減らすこともあります。食事や睡眠が最適でなければ、それも大きくパフォーマンスに影響するでしょう。
「そんな当たり前のこと知っとるわ!」と思う方も多いと思いますが、実際にあなたはパフォーマンスが低い日に自分を責めていることはないでしょうか。
例えばアイデアが出ない、話が頭に入ってこない、うまく話がまとまらない、スケジュール通りに進まずタスクリストがたまっていく、どうすればいいのかわからずPCをにらみつけて途方に暮れる。
こういった「うまくいかない」状況において、調子が悪い自分の状態を「悪いこと」と解釈して、自分を責めたことはないでしょうか?

心身の調子が絶好調であり続けることはあり得ません。ただ、それを理解していてもパフォーマンスを発揮しきれない時にあなた自身を責めてしまうのは、「絶好調の自分」を全ての基準にしていることが原因です。
スケジュールを組むときも、常に「絶好調の自分」を前提としてしまいがちです。また、他人と話をするときも仕事をするときも、理想の自分像を無意識に基準としてしまい、それに満たない自分自身を責めて苦しんでしまうこともあるでしょう。
確かに、何もかも絶好調で頭はキレキレ、身体もキビキビ動く日もあります。それもまぎれもなく「あなた自身」です。
ですが、その日の天気や前日に感じたストレス、将来の心配事など、どうしようもないことで負荷を受け、簡単にパフォーマンスが落ちてしまうのが人間であり、それもまた「あなた自身」なのです。
できるなら常に理想の自分でありたいのは人間の性ですが、どうにもうまくいかない自分に対しても、「そんな日もある」と受け入れてあげてください。
その「受容」こそが、あなたの理想を拡張しより良い将来への自信と推進力を育てるのです。














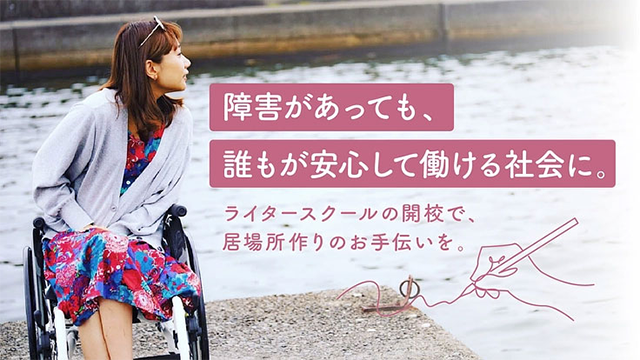









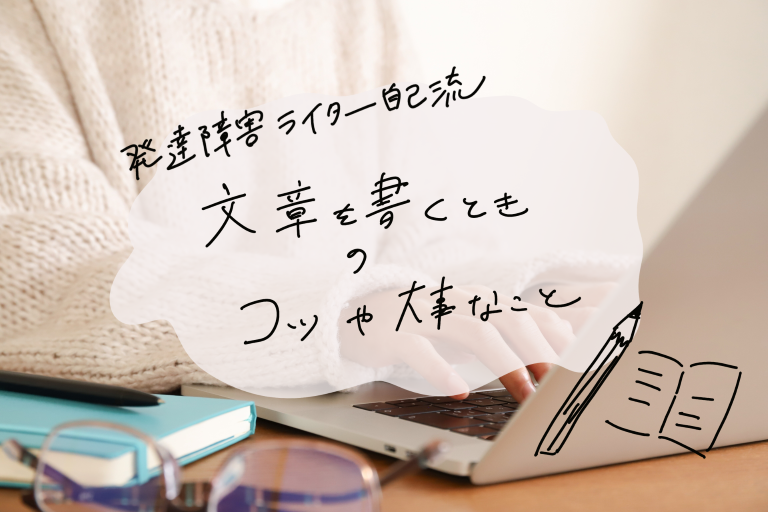









 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック