目には見えない「内部疾患」を伝えることの難しさ
~体育教師の言動から学んだこと
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.5.2
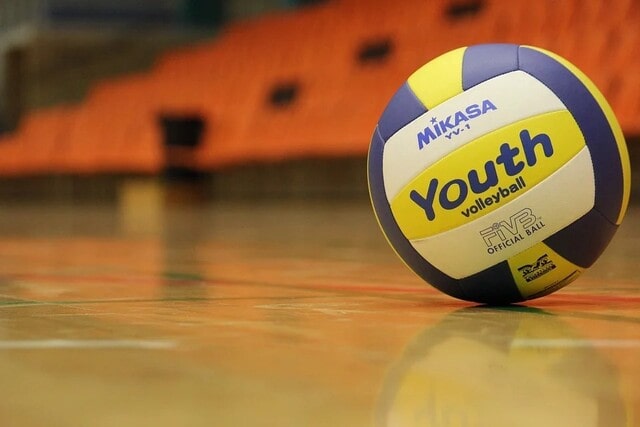
目で見えない病気は人に伝えることが難しく、理解がされにくい。幼少期、私自身、その壁にぶつかったからこそ、「ヘルプマーク」で持病を示さずとも、内部疾患者が生きやすい社会の築き方を考えるようになった。
執筆:古川 諭香 Yuka Furukawa
日常生活が普通にできるからこそ持病が理解されにくくなった
小学4年生の時に行った「フォンタン手術」によって、私の人生は変わった。日常生活で不便やもどかしさを感じることが格段に減ったのだ。
校内でも階段を普通に登れ、息切れせずに歩ける。健常者からしてみれば、当たり前のように思えるそれらが私にとっては尊くて、親に「人生観が変わった」と告げたほど、日常が激変した。
けれど、その一方で日常生活が普通に送れるようになったからこそ、他者に持病を伝えるのが難しいと感じることが増えていった。
中でも、一番悩んだのが体育教師との関係性。手術を受けて、学校に復帰した頃、ちょうど体育教師が変わった。
他の子どもと同じように日常生活を送っているのに、なぜか体育の授業には参加しないヤツ。体育教師の目に、私はそう映ったようで、授業のたびに「本当にこれもできないの?」と嘲笑まじりで何度も聞かれるようになった。
その度に私は、「息が切れて苦しくなるので、できません」と告げ、どれくらいの運動が可能なのかを毎年、学校に提出している「学校生活管理指導表」を見てほしいと伝えた。
だが、体育教師は納得できなかったよう。同級生に「あの子、本当に体育できないの?」「これまでもやってなかったの?」と尋ねたり、私に「手術して治ったんでしょ?」と聞いてきたりした。
同級生たちは私が階段を登れなかった時期を見ているので、そうした事実を体育教師に伝えてくれた。けれど、私に対する“体育の授業をサボっているヤツ”という印象は変わらなかったようで、次第に冷たく当たられるようになった。
そして、ある日、「片付けくらいできるでしょ?授業を休んでる分、動かないと」と、みんなが使った備品の片付けを授業後に言いつけられるようになった。
後に校長先生が止めてくれたため、片付けを命じられることはなくなった。けれど、その時、体育教師はクラスメイト相手に「なぜか、片づけさせるの、やめろって言われたんだよね」と愚痴をこぼしていた。
同級生相手なら「そうなんだ」と納得してもらえていた説明が大人相手だと、こんなにも伝わらないのか。幼いながらそう思った私は、その時初めて、目で見えない病気を言葉で説明することの難しさに直面した。
大人になっても感じる「内部疾患」を伝えることの難しさ

目には見えない自分の病気を、どう人に説明すれば分かってもらえるのか。幼少期に感じた、そのもどかしさは大人になるにつれ、薄れるどころか、どんどん増していった。
例えば、スーパーに設けられている障害者専用駐車場を利用する時。私は普段は使わず、体調が悪い時のみ使用しているのだが、一度、車を止めて降りた瞬間、見知らぬ男性から「健康なら、こんなところ使うな!障害を持ってる人のことを、もっと考えろ」と怒られたことがあった。
金髪で濃いメイクをしていた私は、きっと、その人が思う「障害者像」には当てはまらなかったのだろう。だから、正義感ゆえ、余計に怒りたくなったのだろうなと思った。
また、仕事の取材を終えた帰り道、倦怠感から電車の優先席に座った時には、近くに立っていた女性2人組が「イマドキの若い子はマナーがなってないね」「親は、どんな教育をしてるんだろうね」と、私のほうを見て、わざと聞こえるように話していたことがあった。
私は、日常生活が普通にできる自分よりも症状が重い人に緊急時や日常的に、助けの手が優先的に伸ばされてほしいという想いがあるため、当時も今も、内部疾患であることを伝える「ヘルプマーク」を持ち歩いていない。
だから、それもあって、悲しい誤解に遭遇する機会が多かったのかもしれない。けれど、どんな人がどうしたらもらえるのかが多くの人に詳しく知られているとは、まだ言いがたいヘルプマークを見て「内部疾患者だ」と理解してくれる人は、どのくらいいるのか、そして、それは真の障害者理解に繋がるのかと疑問に思う気持ちもある。
名前も知らない他者を目で見て判断しない優しさを

だったら、どうすれば真の障害者理解に繋がるのだろう。そう考えた末、たどり着いたのは「他者を多角的に見る」という自分なりのアンサー。
私たちは見知らぬ相手や通りすがりの相手を、どうしても目で見て判断してしまう。けれど、自分も目に見えない苦悩を背負っていたり、乗り越えてきたものがあったりするように、名前も知らないその人にだって、抱えているものがあるかもしれない。
正義感が強く真面目な人ほど、一見、五体満足な人が障害者専用駐車場や電車の優先席を利用していると、許せない気持ちになることがあるだろう。その優しい気持ちは、とても尊いものだ。
けれど、もしかしたら、その人にはその人なりの事情があるのかもしれない。そんな風にワンクッション置いて相手を見てみることこそ、根本的な障害者理解に繋がっていくのではないかと私は思うのだ。
よく知らない相手の背景に思いを馳せることは難しい。けれど、そうした人が少しずつ増えていけば、様々な事情や心理的要因からヘルプマークを持っていない人・持たないと決めた人も生きやすくなる。
福祉の輪は、「障害者理解」という難しい言葉を用いなくとも、相手を見る視点を少し変えるだけで広がっていく。持病を何らかの形で表示しなくても、偏見を受けない社会は私たちひとりひとりの意識を変えることで作っていけるはずだ。
























 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック