ADHDの私が抱える3つ働きづらさとその対処法
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.1.26
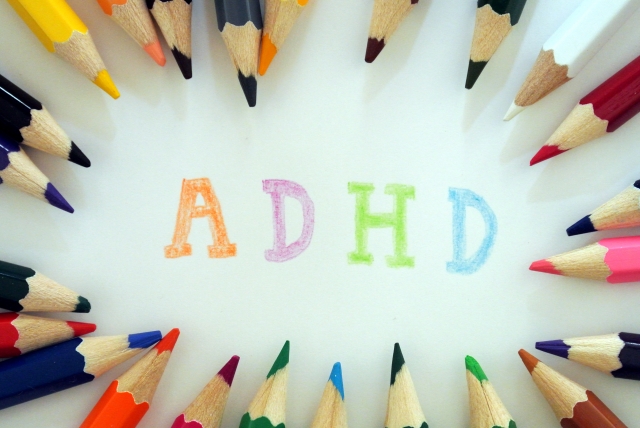
ADHDと聞くと、忘れっぽい、ミスが多い、衝動的な言動が目立つ、片付けができない、遅刻するなど、そそっかしくて抜けているイメージがあるかもしれません。今回はADHD当事者の私が働く上で困ったこと、その困りごとにどう対処してきたかについてご紹介します。
執筆:森本 しおり Morimoto Shiori
発達障害があると、働く上でどんな困りごとがあるのか。同じ発達障害であっても、人によって得意・不得意はちがいます。
ADHDと聞くと、忘れっぽい、ミスが多い、衝動的な言動が目立つ、片付けができない、遅刻するなど、そそっかしくて抜けているイメージがあるかもしれません。
今回はADHD当事者の私が働く上で困った3つのこと、その困りごとにどう対処してきたかについてご紹介します。
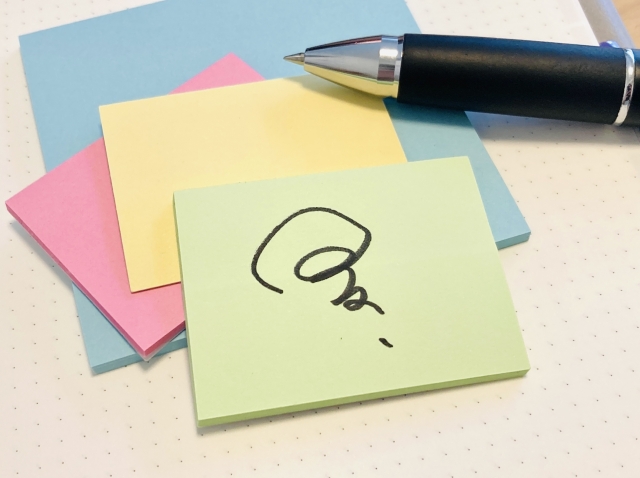
①ギャップが大きい
よく発達障害の人は凸凹と表現されることもありますが、私も例にもれず得意なことと苦手なことの差が大きいです。
得意なことで言えば、私はテスト勉強や言葉の理解力が高いです。WAISテストと呼ばれるIQテストでは平均が100のところ、私の言語系IQは118。面接で話すと仕事ができる人に見えるようです。
一方で、実際に現場で仕事をする速度は他の人よりも遅いです。手を動かすのも不器用で、何かと時間がかかってしまいます。IQテストで処理速度が判る領域では86でした。
得意なところと苦手なところの差が15以上だと発達障害を疑われるのですが、私は30以上開いています。
「これが理解できるなら、この仕事ができるだろう」という見積もりが通用しないので、手を抜いているように見えてしまったりするのが残念なところです。よくないギャップが生まれてしまいます。
②ミスが起きる
以前、ADHDの診断をまだ受けていなかった頃、職員会議で名指しで「最近、ミスが多いから丁寧にやっていきましょう」と言われたその次の日に、同じようなミスをしてしまったことがあります。
当然、「会議を聞いていなかったの?もしくは、この仕事を甘く見ているんじゃない?」と怒られました。ごもっともです。
また、仕事中に何度も「どうしてこんなミスをするの?」と質問されたことがあります。私も何が起きているのかよくわからなかったですが、周囲の人もさぞかし理解に苦しんでいたんだろうなぁと思います。
28歳のときにADHDと診断されて、納得しました。「自分はミスが多い人なのだ」と。
こう認識できるようになってからは、ミスにつながりそうな要素をなるべく省いています。急がず、集中できる状況を整えて、作業を中断せずに確認すれば、少しずつ減らしていけます。
それでもミスを無くすことはできないので、正確性を要求される仕事や最終チェックを担う立場は避けるようにしています。
③他人からの信用を失う
上の二つの結果でもありますが、少しずつ周囲からの信用を失っていきました。
「最初は期待していた」私に仕事を任せてみると、意外と仕事ができず、ミスをする。話をすると理解しているようなのに、実行はできていない。だんだんと周囲からの信用を失っていきます。
周囲の期待と、自分のできることに大きなギャップがありましたが、そこを埋められなかったなぁと思います。仕事で成果を出すか、周りの人に助けてもらうか、何かしらの形でそのズレを解消する必要があったのでしょう。

どうやって、困りごとに対処しているのか?
では、これらの困りごとにどうやって対処しているのか。それは、雇用形態と仕事に対する姿勢を変えたことが大きいのだと思います。
ADHDの診断が降りてから、雇用形態を正社員から非正規雇用に変えました。正社員の頃は管理職的な立場で、広い範囲をカバーする仕事を任せてもらうことが多かったのですが、改めて「向いていなかったなぁ」と感じています。非正規雇用になって、自分に任された仕事に集中できるようになり、ミスが減り、働きやすくなりました。
また、仕事に対する姿勢が、ちょっと抽象的なのですが、「仕事はチームプレーで片付けるもの」と考えるようになったのです。
以前は、立場の影響もありますが、「全部、自分でできるようにならなければいけない」と思っていました。でも、今は大事なことは自分が活躍することではなく、仕事が期日までに終わっていることだと思っています。
いろいろな仕事のやり方は知っておいた方がいいですし、オールマイティーにできたら最高ですが、それよりも職場全体で見たときに仕事がスムーズに進んでいることが大事です。
「全部、自分でできるようにならなければいけない」より「どうすれば仕事全体が進むだろう」や「どうすれば他の人が働きやすくなるか」と考えるほうが働きやすくなりましたし、他の人から感謝される場面も増えました。
もしかしたら、考え方や視点が変わったのは、管理者の仕事を経験していたおかげかもしれません。そう考えると、うまくいかなかった経験も今の糧にはなっています。

まとめ
今回は、ADHDの私が働く上での3つの困りごととその対処法についてご紹介してきました。
振り返ってみると、私の困りごとは「ADHDだから」だけでなく、自分一人だと解決できない課題があったときに、周囲とうまく協力できなかっただけのような気もします。
おそらく、働きづらさは私だけが感じていたわけではないでしょう。一緒に働いていた人も、どうやって私と一緒に働いていったらいいのかわからず、困っていたと思います。
きっと、障害が無くても、自分の力量以上の仕事を任されている人はたくさんいるはずです。本人が困っている場合も、周囲が持て余している場合もあるでしょうが、それでもいろいろな人達が協力して何とか仕事を回しているのかなぁと思います。
私のケースはすべてのADHDの人に当てはまるわけではないと思いますが、参考になればうれしいです。




















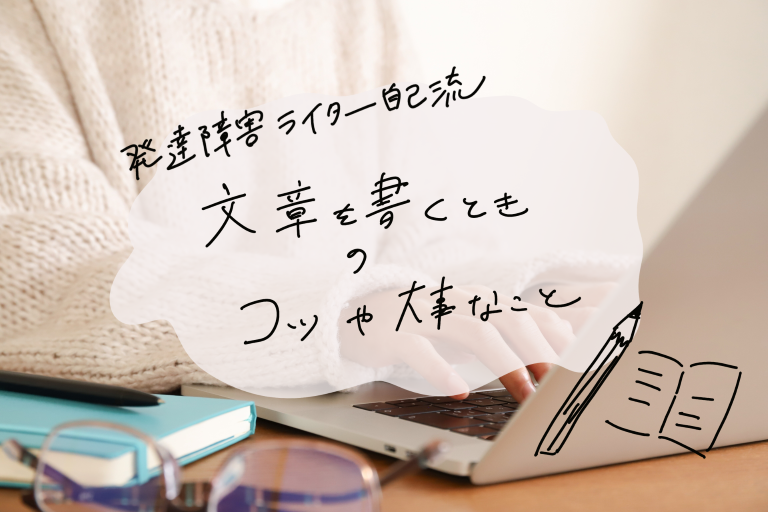

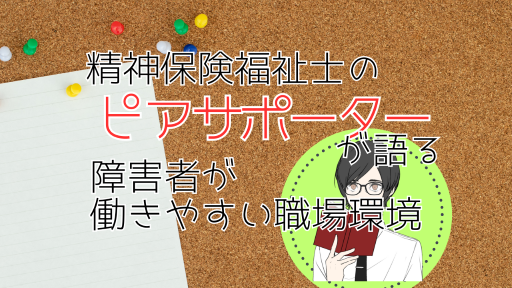
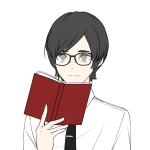
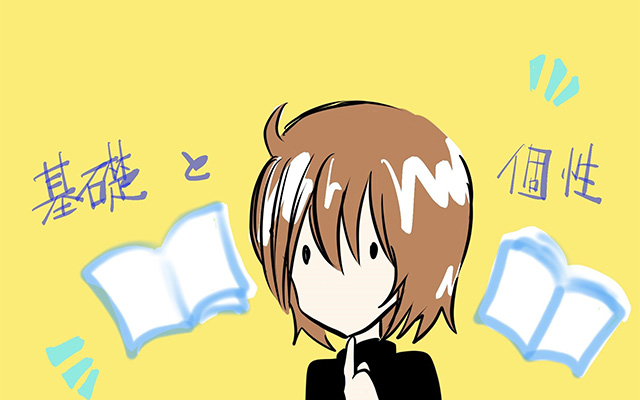








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック