障害があっても「やりがい」や「社会との繋がり」を求めていいの?
~紆余曲折を経てたどりついた私なりの働き方
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.5.19

統合失調症と心疾患を持つ私は、医者から「フルタイムでの普通の勤務は難しい」と言われています。
主婦業すら家族のサポートが必要な時がある私は、やりがいや社会との繋がりを持つことを長年諦めてきました。
紆余曲折あってたどりついた、私なりの働き方を今回はお話します。
執筆:大福 麦子 daifuku mugiko
統合失調症と心疾患を持つ私は、長い間主治医から「フルタイムの普通の勤務は難しい」「大変な役割を負うのは避けてほしい」と言われてきました。
病気や障害ゆえに「疲れやすい」「ストレスに弱い」「無気力」などの症状に、長年苦しんできました。
無気力の症状が落ち着いてやる気が回復すると、今度は「自分を活かす何かをしたいけれど、病気ゆえにできない」というジレンマに苦しむことに…。
専業主婦や母親としてやることがないわけではないけれど、それだけだと社会から取り残された疎外感を拭い去ることが、私の場合はできませんでした。
一方で、主婦や母親としての役割すらサポートが必要で、それらが十分にこなせていないのに、病気の私が社会との繋がりを求めて良いのだろうか?
私の望みは贅沢なのだろうか?と自問自答をする日々がありました。
「私でもできること」を求めてはじめたボランティア活動

「私でもできる何かはないだろうか?」と考えて、まずチャレンジしたのが、自分の空いている時間にできるボランティア活動です。
夫には反対されましたが、どうしてもやってみたいとお願いして、近くの福祉施設で隔週でボランティア活動に従事しました。
障害がある方の散歩のサポートや本の読み聞かせ、リハビリの見守りなどをしました。
自分の体調との兼ね合いで、2時間という短い時間になりましたが、久しぶりに外の社会と繋がりを持てて、「私にもできることがあるのかもしれない」と思える充実した日々でした。
しかし、それも短い期間で終了します。
次女の障害(境界知能)が発覚したからです。
次女の療育へ通わなくてはいけなくなった私は、夫から「外のことより家庭のことに集中してほしい」と言われて、ほんの数か月でボランティア活動をやめることになりました。
没頭できる「趣味」をみつけて心の穴を埋めようとする

次女の療育通いも落ち着いたころ、没頭できる趣味があれば、やりがいや生きがいが見つかると同時に、社会とも繋がれるかもしれないと考えました。
そして、自分の興味がある分野の習い事を探しました。
「絵画教室」はどうだろうか…?
しかし働いていない私には、習い事をするお金がありません。
経済的に難しいというハードルがあり、これも断念。
では、お金がかからない趣味なら?と今度は英語の学習に熱を入れました。
勉強ならばお金はたいしてかかりません。
英語の文法を学びなおしたり、英語の簡単な記事を読んだり、いろいろやりましたが、勉強は孤独な作業で、社会の中で役割を果たしているという実感には繋がりませんでした。
趣味としては最適でしたが、自分の心の穴は埋められませんでした。
精神疾患の当事者会で言われた一言に感動

不完全燃焼のモヤモヤした思いを抱える中で、精神疾患を持つ人が集まるオンラインの当事者会に参加しました。
一人一人が悩みごとや思っていることを発言するなかで、私は「主婦や母親としての役割すらサポートが必要なのに、自分のやりがいや生きがい、社会との繋がりを求めて良いのだろうか?」と、心の内を吐露しました。
「お母さんが活き活きとやりがいや生きがいを持って、社会で活動する姿をみせるのは大切なことだと思います。活動した分、家族に感謝して還元していけば良いと思いますよ!」
参加者の温かな言葉に感動!
障害や病気を抱える私でも社会との繋がりを求めても良いし、主婦や母親業以外のやりがいや生きがいを求めても良いと肯定してもらった気がして、心のおもりが取れていくのを感じました。
パラちゃんねるカフェのコラム執筆を通して見つけたやりがい

紆余曲折のありましたが、ふとしたきっかけで、パラちゃんねるカフェのコラム執筆の募集をみつけて、勇気を出して応募しました。
コラム執筆の応募を通して、Webライターという職業を知り、もともと書くことが好きだったことと、自分の体調との折り合いをつけやすい働き方ができるかもという期待があり、この職業に挑戦しています。
大変なこともありますが、「自分ができる何か」を見つけたという実感があります。
ようやく社会と繋がることができ、納得のいく私なりの働き方を見つけました。
病気や障害があることで、社会と繋がりたくても繋がれない、はがゆい思いや、やりがいや生きがいを求めることすら罪悪感に感じてしまうことが、障害者にはあるかもしれません。
サポートを受けなくては日常が過ごせないという思いが、社会参加への足枷になることがあります。
サポートが必要な人でも、多様な生き方や働き方が認められる社会になれば、引け目を感じないで、社会で自分の力を発揮できる人が増えるでしょう。
それはきっと、今よりもずっと誰もが幸福を感じやすい社会なのではないでしょうか。














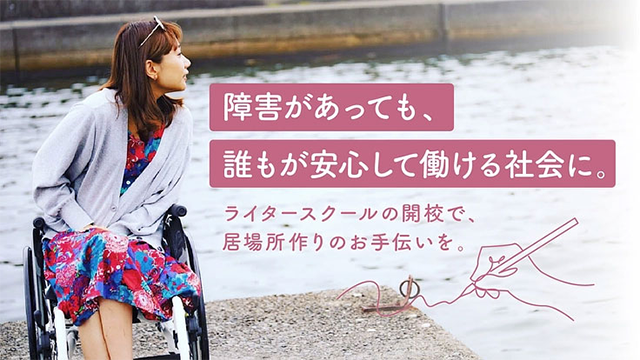







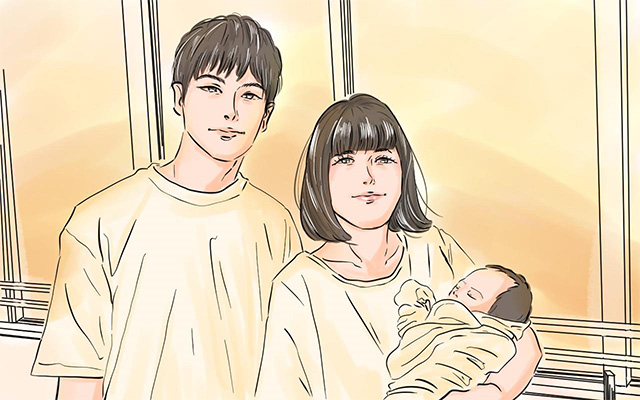
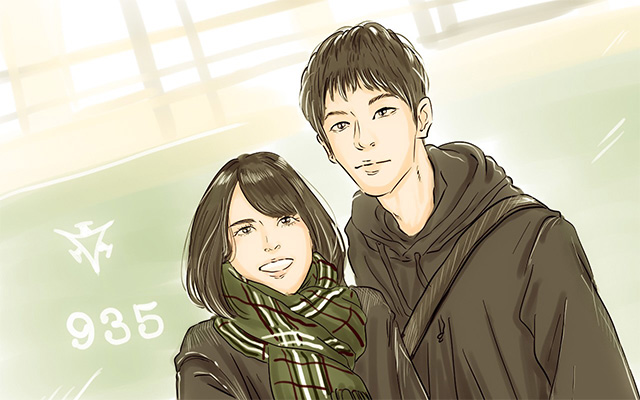








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック