不安症と闘う子供のお話。
![]() 1
1
![]() 1
1
2023.5.26
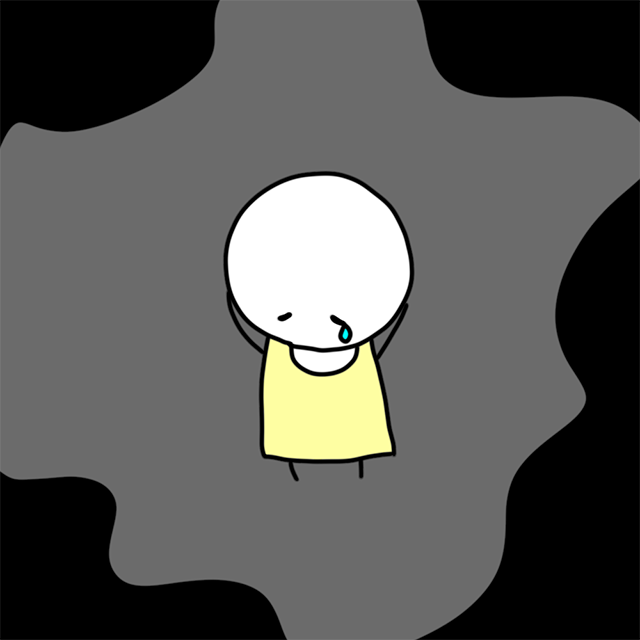
幼い頃から不安症と闘う私の子供。
これまで治療や服薬、たくさんの心理的アプローチを重ね、だいぶ和らいできましたが、新年度は毎年不安が強くなります。
きっとそんなお子さんも多いかと思います。
我が家、今年は特に症状が悪化。数年分くらい後戻りしたような状態です。
そんな我が家の最近の日常についてお話したいと思います。
執筆:愛
何が不安?
元々、新しい状況や予定変更に対する難しさがある中で、特性からくる不安もありますし、ママ(私)が死んでしまうのではないかという不安まで、悪い方に考えられるものは全てが不安になります。
例えば学校での不安。
給食が食べられるか(味覚過敏のため)。
口に入れてオエってなったら…
残していいって言われてもほんとに良いのか。
友達に食べるのが遅いことや残すことに対して何か言われるのではないか。
鼻炎の症状やチックがひどくなったらどうしよう。
先生が出張でいないかもしれない。
代わりの先生が理解のない先生だったらどうしよう。
その先生が給食のことも知らなくて残せなかったら。
勉強が分からなかったら。
先生の話が分からなかったら。
友達が他の友達のとこに行ってしまって1人だったら。
ママがいないから助けてもらえない。
お腹が痛くなったら。
嫌なことされた時に言えない。
泣いてしまったら…
など、考えつくもの全てが不安材料となります。
そのほとんどが過去に経験したものなので、余計にリアルな不安になってしまいます。経験していなくても、想像できるものは全て不安になります。
もちろん子供は、できていることもたくさんありますし、力もちゃんとあります。
でも、そんなのも見えなくなってしまうほど、心の中の『不安』は大きく大きくなります。
元々自閉症、こだわり、癇癪(パニック)、感覚過敏もあるので、どうしてもその場所から身動きが取れなくなってしまうことは小さい頃から多かったです。
別のコラムで書く予定ですが、こだわったり身動きが取れなくなる部分に対しては、これまでも治療や多くの心理的アプローチを続けてきました。
子供自身も頑張ってきて、その甲斐あって大きく成長し、そろそろ私との距離も離れていく段階に入るであろう…と思っていた矢先、今回の数年分後戻りしたような状態になりました。
でも、これは後戻りのようでそうではないと、そう思っています。
この先大きく高く飛ぶための、深い深い屈伸なのだと、これは直感的に感覚的に私は感じています。
なので、この山をどうしたら乗り越えられるかを毎日考えています。
そして、まず始めたのが、実は以前も我が家でやっていたお菓子くじです。
子供から「またやりたい」と言われたのもありますが、「学校を頑張るためのご褒美」と、「自分で自分にご褒美をあげて心を元気にする感覚」を育てるために、もう一度お菓子くじをやってみることにしました。
まずお菓子に紐をつけてダンボールに入れます。小さなかわいいチョコなどからちょっと豪華なお菓子まで、表からは見えないように隠します。

くじを引く回数について、今回ルールは特に決めませんでした。
その日の頑張った感覚と引き当てた金額の程度(笑)、様子を見ながら私から回数を足したり、子供自身にあと何回引くか決めさせています。
一気に全部引いてしまうと次の日のご褒美は無くなってしまう。
けど、今日の頑張った感じはどのくらい?
心が嬉しくなるのはどのくらい?
日々問いかけを続けながら、子供自身に自分を見る力が育っていくようにと思っています。
押して引いて…
学校はちょこちょこお休みしたり、早退したり、毎日様子を見ながらどうするかを決めています。
ここのところ、登下校は付き添いをしています。
不安なことに固執してしまうので、特に登校の道のりは気を逸らし作戦を続けています。
「道のあそこに立っているものは何に見える?クイズ」や「古今東西ゲーム」、あえて「不安なこと」をクイズにしながら登校しています。
例えば、「今日は先生が出張かそうでないか」、「◯◯の授業は何時間目か」…など、帰宅時に結果を子供から聞いて、勝敗を決めます。
これは、今まで癇癪やこだわりへのアプローチを子供も積み重ねてきて、以前より緩和してきたからこそできるクイズだと思います。
でなければ、クイズどころではなく、まず泣き叫んで家から出ません(笑)。
そして子供自身の勝負事が大好きだという性格も大きいです。日頃からも勝負することが多いので、こういった場面でも役に立ちます。
ゲームをしながら涙を堪えていたり、バイバイの時は泣いていることもあります。
それでも今のところは下駄箱でバイバイができていて、呼び出しもありません。本当によく頑張っていると思います。
その他にもいくつか子供が踏ん張れそうなものを用意して登校しています。
私は、上の子供2人ですでに不登校を経験しているため、今は少しの余裕もあります。
それでも尚、燻る想い。
母としての気持ち
どこまで受け止めてあげればいいのか。
どこまで頑張らせたらいいのか。
泣いているのに…
私はどこまでしてあげればいい?
もう全部受け止めよう。
言ってるままを全て。
抱きしめてあげよう。
また泣くの?
さっき話終わったのに…
また?
また?
また?
一日中泣いて…
私もしんどくなってきた…
いい加減にうるさい!!!!!
ママだってしんどくなるよ…
ここは励ましなのかな?
ここは強めに言ってみるか?
ここはただ聴けばいいかな?
今が大事な時。
大丈夫。
この子なら。
大丈夫。
私なら…。
そんな風に、様々な気持ちが入れ替わり…私も人間なので、時にはしんどくもなります。
自分の切り替えと回復がとても大切なのですが、最近はイライラも自由に表現しています。
私も私として表現することは、子供の学びになるからです。
家や私が居心地が良すぎると、この子は外に出られなくなるなという感覚もあり、でも、受け止めなければ心が壊れてしまうという思いもあり。
毎日ここまで押して、ここは引いて?と、1人考えながら子供と接しています。
子供の人間関係の構築と私の療養のために通っていた学童も、今回の不安症がひどくなったことをきっかけに辞めることにしたので、今後子供との時間がより増えます。
多分、1番大変なのは、私の回復なので、そこの対策を考えようと思います。

子供には、親である私以外にも、気持ちを吐き出せたり、離れていても大丈夫だという感覚を、焦らず大切に構築していきたいと思います。
また、いつ、少し前の子供の笑顔を取り戻せるのかは分かりませんが、絶賛、親子で奮闘中です。






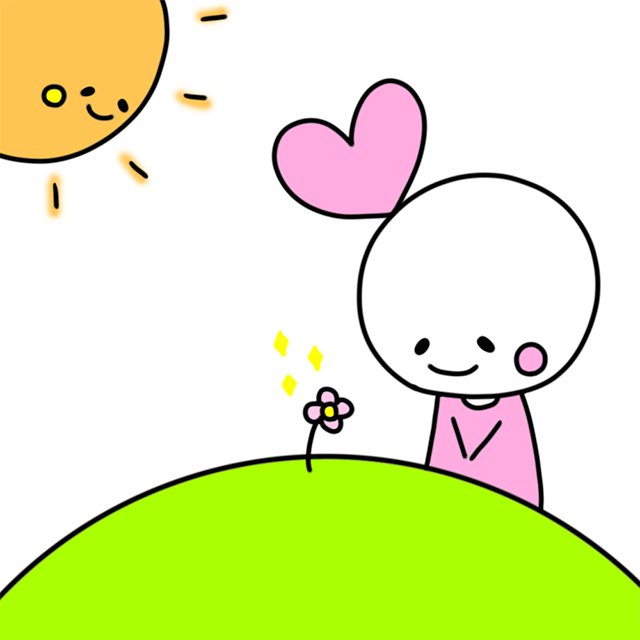
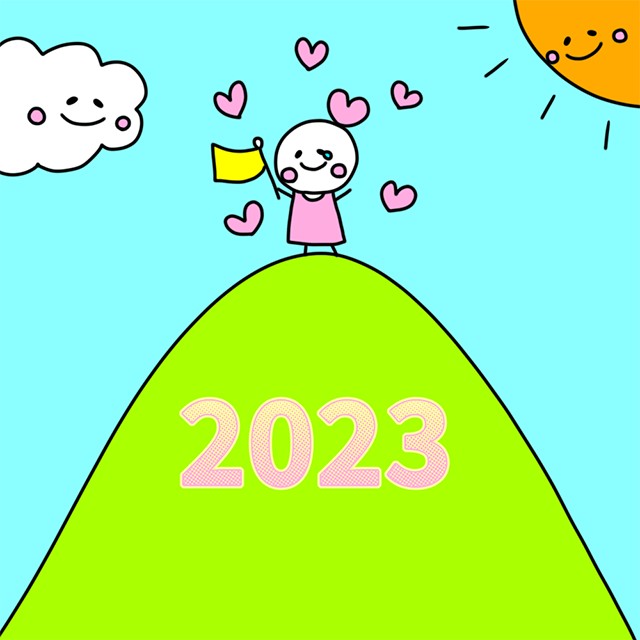
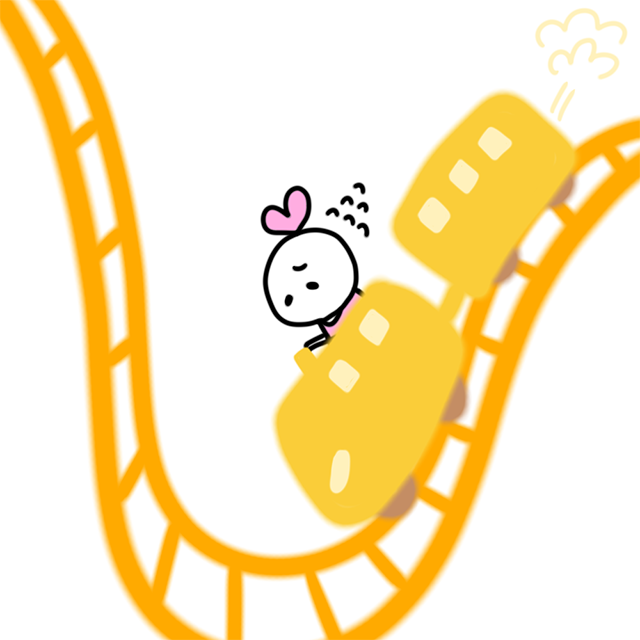
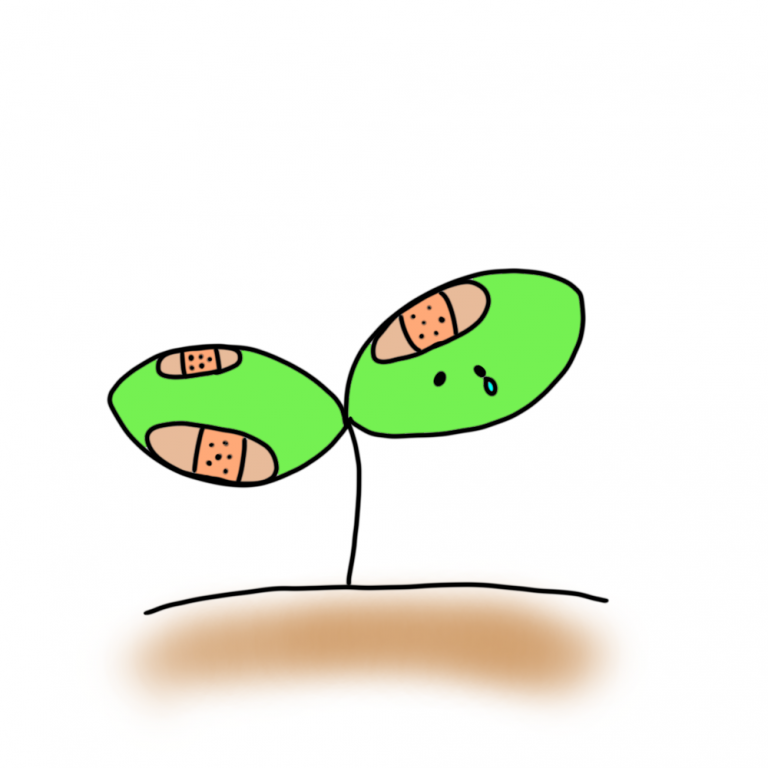











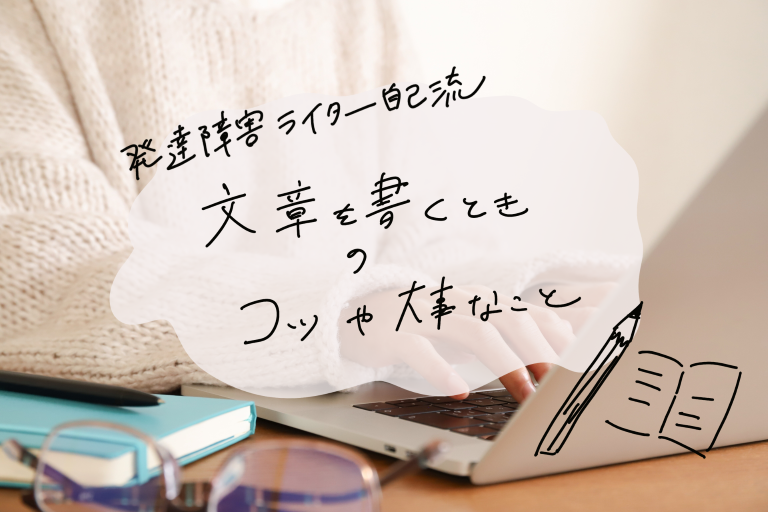









 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック