自分のオールは自分で担う
~医師や支援者とのかかわり方について~
![]() 1
1
![]() 1
1
2021.8.28

「あなたは発達障害ではないです。話し方も普通だし、発達障害がある人は大学を卒業できない。新社会人として甘えが出ているのでしょう」
2016年、大学を卒業して小さなWeb出版社で働き始めて数か月。初夏のことでした。働く中で違和感をおぼえ、とある大手メンタルクリニックを訪れていた私は、診察が始まって早々に医師からこのように告げられました。
執筆:大河内 光明 Komei Okouchi
初老の医師の態度は頑なでした。精神安定剤を出すことはできるが、知能検査には回せない。少し粘って交渉しましたが、答えは変わらず。半ば門前払いに近い形で、診断してもらうことはできませんでした。
その後、発達障害の「疑いあり」の診断を経た後、ようやく「注意欠如障害と自閉症スペクトラム障害の併発」という確定診断を別の専門クリニックで得たのは2019年のこと。
その時までに私は三度の失職を経験しており、精神的に限界の状態でした。
あの時もっと強く医師に訴えていれば。真っ暗闇の部屋の中で悔しさを押し殺して泣いたのをよく覚えています。

今回こういった経験を踏まえて皆さんにお伝えしたいのは、「自分のオールを人に任せるな」ということです。その後、各種支援や福祉に繋がり、障害者雇用で働く中でもこれほど大切なことはないと思っています。
それまで「健常者」として生きてきて、障害者支援の制度など右も左もわからない中で、医師や支援者(支援機関の担当者)のアドバイスはとても重く響きました。しかし、そういったスペシャリストの方々も、決して私たちの人生全てを知っているわけではありません。
何を選択し、どう生きていくか。医師や支援者は水先案内人ではあるけれども、かじ取りを担っているのはあくまで私たち当事者です。時には意見を戦わせ、自分の意思を押し通さなければ道が開けない時があります。
この記事では、私の体験談を踏まえてそういったお話をできればと思います。

さて、お話を元に戻すと、確定診断が出たあとの私は、いったん地域の支援機関に赴きました。その後、障害者手帳を申請し、障害者雇用での就職を検討している最中の2020年、新型コロナウイルスが大流行する事態となりました。
ここで(支援機関の)担当者と私の意見はわかれました。担当者の意見としては、コロナウイルスの終息を待って、ハローワークを中心にじっくり腰を据えて企業を見ていこうという方針。
障害者雇用での就職が初めてであるということから、焦らずやってもらいたい。ハローワークでの就職活動であれば公的支援機関とも連携を取りやすいので、ということでした。
私自身はこの流行は収まらないし、障害者用のハローワーク求人で納得いくものが見つからないので、自ら転職エージェントを利用し、短期集中で就職してしまおうという気持ちが強くありました。
結局、私は自分の意見を通す形で、とある民間企業に就職しました。
また、就職の際には「副業が可能であるか」という点も私としてはこだわりたいポイントでした。まだライティングの副業を始める前で、具体的なプランは何もなかったのですが、障害者雇用での給与水準を考えるといずれは始めるだろうなという予感があったためです。
その後プロのライターさんと知り合い、ライティングを学ぶ機会を得るのですが、それに際しても、(支援機関の)担当者としては心配の方が強かったようです。
「お金のやり取りでトラブルにならないか」「本当に本業が疎かにならないか」と何度も警告をいただきました。この点では担当者の方はかなり難色を示されていて、議論を重ねたのをよく覚えています。
ちょうどこの記事を書いている時点で就職後1年。私と(支援機関の)担当者、企業側で面談をする機会があり、その帰り道に
「結局、大河内さんの選択は正しかったですね。コロナで実習や面接も完全にストップしているので、あの時期に就職できたのは結果的に良かったと思います」
と担当者の方から言っていただきました。
副業の件に関しても、「気晴らしになっているようですし、いいですね」というお話になりました。
私自身、あの時押し負けていたら、いまだに就職できず、ここでこうして原稿を書いていることもないのだなと思うと、自分の決断は正しかったのだと強く感じています。

こうした経験を踏まえて思うのは、「自分にとって必要なことだと感じたならば、説得的に主張してほしい」ということです。
診断が必要ならば、困りごとを書き出して、いかに自分が生活に不便を感じているのか医師に強く訴える。支援者(支援機関の担当者)とは歩調をあわせることが必要ですが、必ずしも人生の選択すべてに許可を出してもらうことはありません。粘り強く説得的に主張し続けていくこと。
支援をされる上で、基本的にはプロフェッショナルの意見を尊重した方がいいとは思いますが、この点は意識したいものです。
医師や支援者との信頼関係とは、唯々諾々と従うことで培われるのではなく、お互い主張をしあって落としどころを模索し、尊重しあうことで育まれるのだと思います。
Text by
Komei Okouchi
大河内 光明


1994年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、web出版社、裁判所職員を経てライター。発達障害(ADD、ASD)当事者。






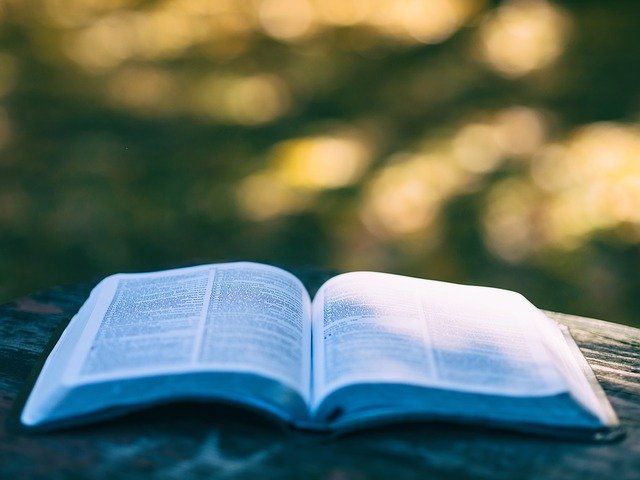











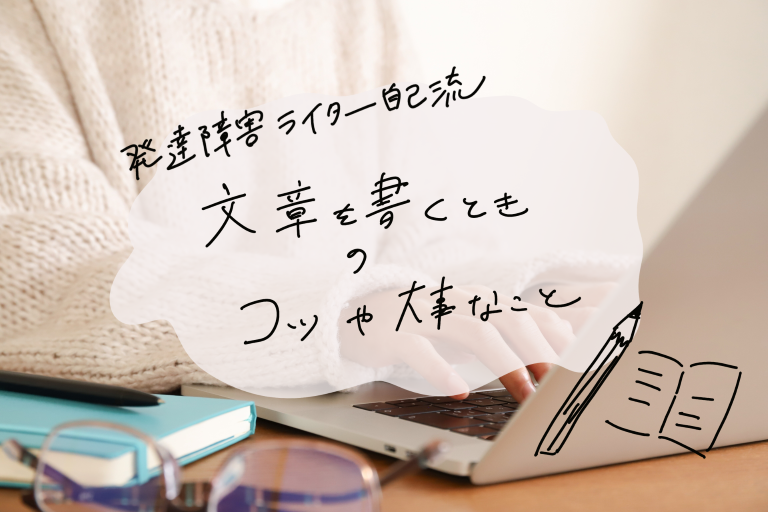

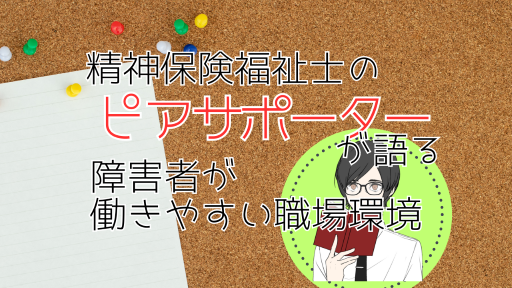
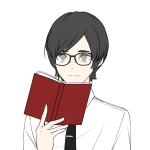
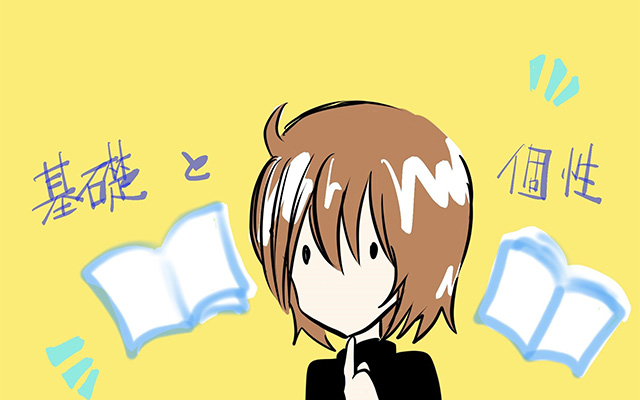








 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック