二つの障害を抱えても、社会に参加し、“働く”ことはできるのか。
![]() 1
1
![]() 1
1
2021.12.18

二つの障害を抱えても、社会に参加し、“働く”ことはできるのか。
答えは「yes」だ。
なぜならその当事者である中川は社会に今でも関わり、働き続けられている。
このコラムは聴覚障がいと精神障がいどちらかにあてはまる人にとって有益な情報になるのではと思って記す。
そのどちらでもない一般人には、「ほぅ、このような人もいるのだね」と見聞の一つになれば幸いである。
執筆:中川 夜 Yoru Nakagawa
人によっては様々なバックグラウンドを持って生活をしているということを私たちは忘れがちだ。日本に生まれたなら、自動的に幼稚園、小学校、中学校、高校まで行ったあとで、枝分かれする。専門学校か大学、それから何かしらの企業で働くルートを辿るのが一般的である。
私は高校以降、元々、精神の気分の浮き沈みが激しく、その結果、大学を中退した。そして、24歳まで外部との関わりを極端に恐れ、精神病を発症した。
その6年後、30歳になった現在、聴覚障がいと精神障がいの二つの障害を持っている私はライターとして執筆業をしている。6年前とうってかわって、社会との関わりを実感しながらいただいた仕事をこなしている毎日で満足感は大きい。
24歳から現在までのお話をすることで、聴覚障がいと精神障がいどちらかにとって、ナビゲーターになればと思う。
流れとしては、下記の通りだ。
- 1.統合失調症を発症し措置入院で半年ほど病院で過ごす。
- 2.1年ほど週1で精神のデイケアに通う。
- 3.B型作業所に1年通所する。
- 4.A型作業所に1年ほど通所する。
- 5.一般就労で1年ほど働く
- 6.半年のトライアル雇用を通して、株式会社にて事務補助を1年ほど勤務する
- 7.ライターとして活動を始める
一つずつ説明したい。

1.統合失調症を発症し措置入院で半年ほど病院で過ごす。
病院内でも作業プログラムがあるので参加するかは無理しなくても良い。
これに関して、この時期はゆっくり休んでおくのが良いと思う。障害を認識して受け入れて受容できるかどうかが社会復帰の要になるはずである。たとえ、理不尽だと思っても。
2.1年ほど週1で精神系のデイケアに通う。
私の場合は、病院と保健センターの二つのデイケアに通っていた。
病院では、1時間半ほどの革細工を作るプログラムに通っていた。他には英語で歌ったり、パソコンを使ったり、絵画等のプログラムがあった。病院では利用者が沢山いたので、聴覚障がい向けのサポートは満足いくほどではなかった。
逆に保健センターでは、保健師さんが親身になってくれたり、要約筆記者(話の内容を要約し文字にして伝えてくれる)が配置されたりというサポートがあったおかげで、利用者同士での交流がしやすかった。
人によってはどのくらいの期間で次のステップに入れるかはその時の症状の重さによる。私の場合は、結果的に1年かかった。

3.B型作業所に1年通所する。
聴覚障がいの就労継続支援福祉施設に入所した。精神系の聴者のB型作業所ではなく、聴覚障がいに特化した施設にした。
作業の内容は、アナログな作業がメインだった。軽作業つまり、商品にシールを貼る、梱包する、封入する作業が簡易な業務メインである。また裏に畑があったので簡単な農作業も行った。
工賃も幾らかいただける。料金は、詳しくは覚えてないのだが、9時00分~16時00分(休憩1時間)作業をし、週に5日通って、月に一万円ほどだった。
※B型作業所…就労継続支援B型。障害や難病のあり働くことが困難な方が、雇用契約を結ばず、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービス
4.A型作業所に1年ほど通所する。
こちらでは知的と精神障害がメインの事務所に入所した。
軽作業もあったが、パソコンを使った業務が多かった。WordやExcelを一通り使いこなせると楽かもしれない。
作業所によっては違うかもしれないが、私が入ったA型作業所は、給料がアルバイト並みに同等だった。場合によっては9万円近い月もあった。
また勤務時間も2通り選べた。9時00分~昼過ぎ、9時00分~夕方ほどまで。自分の体調に合わせて選べることも可能だった。
※A型作業所…就労継続支援A型。障害や難病のある方が、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービス

5.一般就労で1年ほど働く
A型作業所から一般就労(勤務先は放課後等デイサービス)に移ったタイミングは、A型作業所で一年勤務したあとだった。こちらは友人を通しての紹介で働き始めることができた。
小学生の子どもの対応とメール対応が主だった。時間は午後から働くことが多くかなり働きやすかった。
6.半年のトライアル雇用を通して、株式会社にて事務補助を1年ほど勤務する
前職は、コロナの影響で、退職することになり、就職活動を始めた。ハローワークに行き、障害雇用でのパート・アルバイト勤務を探したがことごとく「ろう者」だと先方が知ると、お断りをされることになった。
そんなとき、トライアル雇用の存在を知って、その雇用がある会社に絞って応募したら、一社すぐに受かった。
仕事内容は人事課の事務補助であった。会社内の手の回らないところを清掃と片付け、Word、Excel、パワポ等のパソコンでの簡易な作成、確認作業と言った感じだった。
7.ライターとして活動を始める
その後、5の放課後デイサービスで知り合った友人2人からの仕事の紹介や斡旋もあってライター業をやることに決めた。
月収はまだ雀の涙ほどだが、やり甲斐と生き甲斐を感じて今に至る。
さて、今回は、24歳~現在まで6年間のステップアップについて書いてきた。次回のコラムでは、聴覚障がいと精神障がいの当事者である中川の思いを伝えたい。
働く上で大切にしていること、働きながら築いた信頼関係や社会から必要とされている実感で「生きづらさ」が「生きやすさ」に変わっていくことなど。障がいを抱え、働き始めることに不安を感じている方に、ぜひ読んでいただきたい。







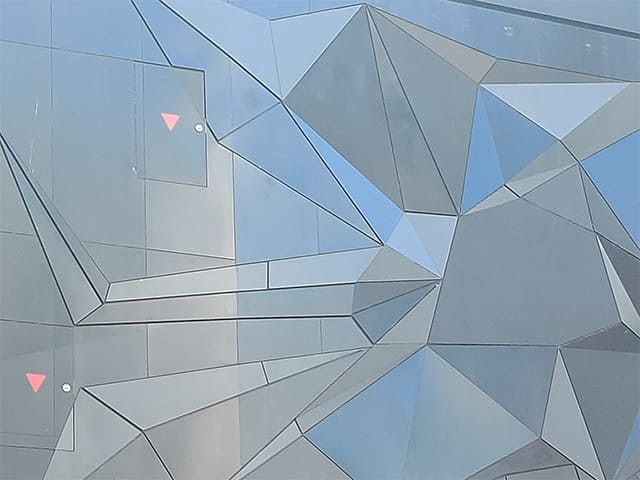

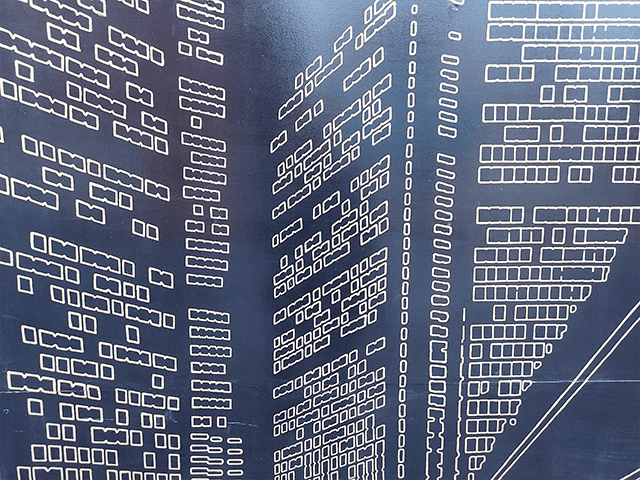



















 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック