全盲の私が体験した職場での配慮について
![]() 1
1
![]() 1
1
2022.11.5

私は全盲の視覚障碍者です。これまで盲学校を卒業してから25年ほどあん摩マッサージ指圧師として働き、その後は3箇所の公共機関で働いてきました。今回は私が職場に求めた配慮について書いてまいります。
執筆:小川 誠
私は全盲の視覚障碍者です。これまで、盲学校の理療科を卒業してから25年ほど、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(今後 あはき師と略します)として働きました。その後は1週間に3か所の公共機関で働き、2か所でオンラインでの仕事をしております。
その間に、職場に配慮を求めたこともあり、自ら環境に慣れていったこともありました。
今回は、あはき師として病院で働いていたときのことと、あはきの仕事から離れてから現在勤務している3か所の職場に共通する配慮について書いてまいります。

病院に就職した直後は不安感が大きかった
全盲の私は盲学校の理療科であん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての勉強をして、国家資格を取得しました。あん摩マッサージ師とは、あん摩、マッサージ、指圧の技術を用いて患者さんの身体に起こる変調を緩和するお仕事のことです。
私の初めての就職先は病院でしたが、就職した直後は様々な不安を抱いていました。「患者さんがどこにいるかわからずぶつかってしまうのではないか?もし、怪我をさせてしまったらどうしよう。」など、心配が絶えませんでした。
リハビリ室で求めた配慮
勤務先であるリハビリ室の広さは、大体30畳程度の広さで、ベッドやさまざまな種類の治療器が配置されていました。
私が困ったのは、室内の移動と、物の位置を覚えること、そして「患者さんと衝突してしまうのではないか」ということです。
室内の移動については、慣れるまでは移動を助けていただきました。手の空いている職員に手引きしてもらいながら、少しずつ覚えていきました。自分で治療器の位置などを参考にしながら移動出来るように工夫しました。
治療器の操作ボタンについては、同じような形のボタンが多く並んでいたので、判断に迷うことが多かったです。「よく使用するボタンにテープで印を付けてよいでしょうか」と尋ねたところ、承諾を得られたので、印をつけて自分一人で操作を出来るようになりました。
「移動の際に患者さんと衝突してしまうのではないか」という心配はリハビリ室の他の職員が「まっすぐ歩くと患者さんがいるよ」などと教えてくれたり、患者の方からも「ここにいるよ」と声をかけていただいたりすることで、どうにか解消することが出来ました。
デイサービスでの配慮
病院では、リハビリ室だけでなくデイサービスでも勤務させていただきました。身体の不調を抱えている人に対してマッサージをするという仕事内容は共通していますが、環境がちがえば必要な配慮も変わってきます。
特に、デイサービスは立ち上げのタイミングだったため、施設長と必要な配慮についての話し合いの場が設けられました。
リハビリ室には患者さんが施術を受けに来てくれますが、デイサービスでは訪問マッサージのような形で、私がその日にマッサージを予定している利用者さんのところへ移動します。
私からは、1日のマッサージの予定者を事前に教えていただきたいことと、移動する際には次の利用者さんのところまでどなたかに手引きをお願いしたいことをお伝えして、認めていただくことができました。
私自身としては、マッサージの予定者の名前を点字でメモをして効率よく仕事できるように工夫しました。
移動についてはマッサージが終わってもなかなか職員の方の手が開かないときもあり、次の利用者さんまでの移動に時間がかかってしまうこともありましたが、おおむね気にならないくらいでしたのでよかったのではないかと思います。

あはき師から離れてからの現在の状況
現在、月曜日から金曜日までの間、通勤で3か所の公共施設に通勤しております。幸い、3か所とも視覚障碍者を採用している実績があるため、それほど困った事態にはなっておりません。
心がけていることは、視覚に頼らなければならなくなったときに、はっきりどのようなことで困り、どのような助けを必要としているのかを伝えるようにしているということです。
当たり前なことではあるのですが、これがけっこう難しいのです。晴眼者の職員との認識の違いが起こることもあります。そのようなときは、何度か説明の仕方を変えながら認識の違いを解消させて、助けを得ております。
室内の移動については、採用前の面接時に「通路の部分には物を置かないようにしてください」とお願いしてあります。やむを得ず、物を置かなくてはならない場合は、一言声をかけていただくようにしてもらっています。
スクリーンリーダーで読み取れない文書のときの対応
私は、全盲なのでパソコンを操作して業務をする際は、画面上の情報を音声で読み上げてくれるソフトであるスクリーンリーダーに頼っています。
ただ、スクリーンリーダーでは読み取れるファイル形式とそうでないものがあります。たまに読み取れないファイルが社内メールで添付されて送られてくることがあり、その際には、スクリーンリーダーで読み取り可能なファイル形式をお伝えし、変更していただいております。上記の対応も迅速に行って下さるので、大変ありがたいです。

まとめ
障碍者がお仕事をする上で大事なことは、こちらが求める配慮がうまく実現され、その配慮を実際受けたときの感覚とのミスマッチが生まれたとき、その後継続的に話し合いを進めることができるかということだと思います。
障碍者側、雇用主側ともに信念が必要になってまいりますが、お互い可能な限り話し合って双方にとっていい雇用環境を整えていければ良いのではないかと思います。
私は「雇用主側の中で視覚障碍者はどのようなことができるのかわからないということで、雇用が進まない事態になっているのではないか」と考えています。
こちらからも、視覚障碍者ができることをしっかり伝え、雇用側もそれを理解して最良な雇用関係を構築して行けたら良いと思います。
そして、今後このような良好な関係が実現していければ、多くの視覚障碍者が活躍出来る業種の拡大も期待できるのではないかと思います。

















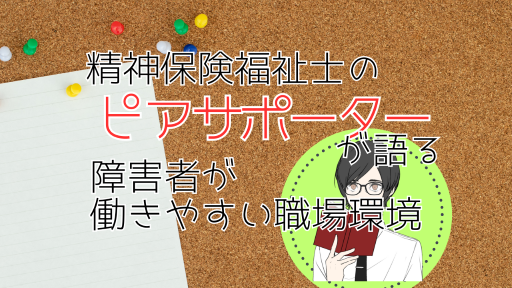
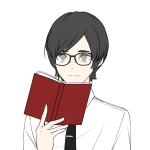













 新着記事
新着記事




 いますぐチェック
いますぐチェック